加藤智太

加藤智太
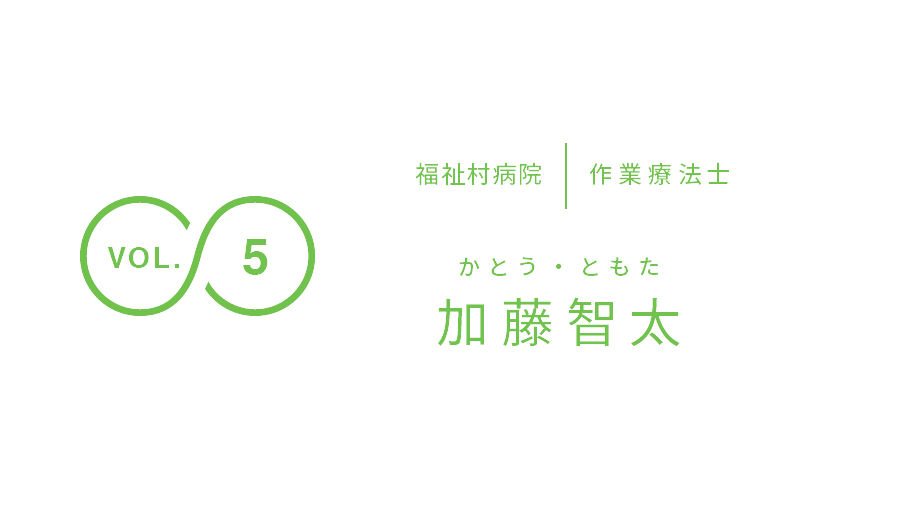
最初に、作業療法士の仕事について教えていただけますか?
現在、福祉村病院のリハビリテーション部門には、理学療法士、言語聴覚療法士、作業療法士、臨床心理士、音楽療法士が在籍しています。どの療法士もそれぞれ患者さんのリハビリのお手伝いをするという点は同じですが、そのなかでも作業療法士は、飲食、排泄、着替え、入浴といった日常生活動作の習得の支援を行っています。たとえば、手をケガして、箸を持ってごはんを食べられなくなったとしましょう。それを、レクリエーションやゲームをしながら、もう一度できるようにするのを支えるのが僕たちの仕事です。このほか、患者さんの心のケアも作業療法士の大切な役割の一つです。

やりがいを感じるのはどんなときですか?
担当した患者さんが退院されたり、それまでできなかった動作ができるようになったのを見たりしたときは嬉しいですね。以前担当した患者さんで、ごはんをスプーンですくって口に運べない方がいました。でも、あるとき、スプーンでプリンをすくって食べられたんです。その方は会話ができないんですけど、表情からとても喜んでいることが伺えて、僕も心底「よかった」と思いました。ただ、それがやりがいかというと少し違います。回復されたのは患者さん自身ががんばった結果であって、僕の力ではないので。「よかった!」と嬉しくなって、もっともっとリハビリのお手伝いをしたくなる。そんな感じでしょうか。
最後に、今後の目標などがあれば教えてください。
現在、福祉村病院では「認知症リハビリプロジェクト」を実施しています。これは、患者さん一人一人に合ったリハビリプログラムを提供しようという試みで、たとえば、大工仕事が好きだった患者さんがいたら、その人にはDIYを取り入れたリハビリプログラムを提案するというものです。患者さんはそれぞれ生まれ育った環境も違えば好みも違います。また、好きなプログラムをやったほうが、症状や精神状態が安定するといわれています。ですから、今後はこのリハビリの個別化に力を入れていけたらと考えています。
あとは、もっと地域に出て行く機会を増やせたらいいですね。訪問リハビリももちろんですけど、退院して自宅で暮らしている元患者さんにふらっと会いに行って、「久しぶり!元気?」とおしゃべりできたらいいなと思っているんです。
仕事で心がけていることはありますか?
患者さんと接するときは、“患者さん”としてではなく、“人”として接するよう心がけています。相手を患者さんとして捉えてしまうと、どうしても、「リハビリをしてあげている」という意識になってしまうからです。「してあげる」という考えでいると、「こんなに一生懸命やってあげているのに……」という気持ちが生まれます。実際、後輩から「自分は精一杯やってあげているつもりだけど患者さんが応えてくれない」という相談を受けたりもします。僕もまだまだ未熟なので、そういう気持ちになってしまうときは、正直ある。でもやはり、「してあげる」「やってあげている」という気持ちじゃダメなんですよね。そもそも、患者さんの回復をサポートするのが僕らの仕事で、それで給料をいただいているわけですから。
だから、僕は患者さんを“人”、つまり、相手を家族や友人だと思うようにしています。家族や友人と同じように接すれば、リハビリを「してあげる」ではなくて「一緒にやっている」という意識になれるし、何より、間違った対応をせずにすむような気がするんです。最近よく「医療もサービス業だ」と言われますし、確かにその通りなんですけど、それ以前に、人として接することが大切なんじゃないかと思っています。
また、福祉村病院に入院されている患者さんは高齢者がほとんどです。回復されて退院される方ももちろんいるけれど、そうじゃない方も多い。僕が患者さんと接している時間は、患者さんにとって人生最後の時間かもしれません。人生の最後という貴重な時間に関わらせてもらうのなら、リハビリとはいえ、できるだけ楽しんでもらいたい。そう思いながら仕事をしています。

