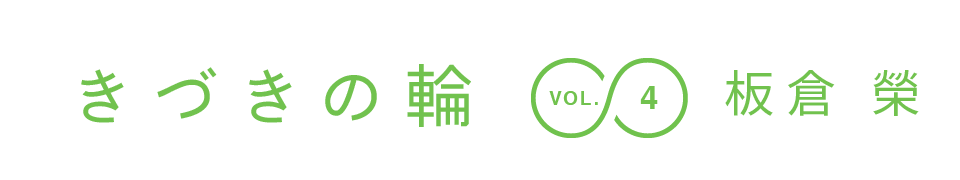板倉榮

レジデンスなかま管理人
板倉榮

板倉さんは福祉村病院の前身である山本病院、そして福祉村病院の事務長を歴任されています。当時の福祉村の様子を教えていただけますか?
私が山本病院に医療事務員として採用されたのは1974年のことです。山本病院は当時、脳卒中のリハビリを専門としていまして、患者さんも増加の一途でしたから、私たちスタッフは「これからは病院をもっと大きくしていこう」と思っていたんです。ところが、山本孝之先生(現:理事長)は違いました。「社会福祉法人を設立する」と言うんです。スタッフはみんな、「なんで?」と首をかしげていましたね。
これは後から知ったのですが、先生がそのような決断をされたのには訳がありました。あるとき、退院した患者さんが、病状が回復されていたにもかかわらず、一人暮らしだったために孤独死されるという事件が起こったんです。先生はそれがきっかけで「退院が悲劇の始まりにならないように、患者さんが退院後も安心して生活できる施設をつくらなければ」と思うようになり、社会福祉法人を目指されたと聞いています。
社会福祉法人の認可を受けるのにはずいぶん苦労しましたよ。資金が足りなくて、先生の私財を充てたりして、なんとか認可を得ることができたんです。医師が足りなくて、スカウトに行ったりもしてね。私が働き始めてから1987年に退職するまでの13年間はまさに、福祉村の成長期だったといえるでしょう。

板倉さんが考える、福祉村の“強み”を教えてください。
知識も経験も豊かなスタッフが揃っている点ではないでしょうか。福祉村には医療、福祉、介護それぞれのスタッフがいますから、認知症の患者さんも、障がい者の方も、受け入れることができます。こうした取り組みは、ほかではなかなかできません。
私は1987年に一度退職し、2010年に再び福祉村に戻ってきました。今は、職員宿舎「レジデンスなかま」の管理人をしています。管理人の仕事は、一言でいえば、寮に住むスタッフが暮らしやすく、なおかつ働きやすい環境を整えること。スタッフはこの福祉村の強みであり宝ですから、とてもやりがいを感じています。
福祉村がよりよくなるために、今後何をすべきだと思いますか?
外来の患者さんをもっと受け入れられる体制ができればいいなあ、と感じています。それから、通院・通所でも入院でもない、福祉村と関係のない方にも、まずは気軽に福祉村に来てもらえる機会をつくれるといいですね。福祉村の中にいる人と外にいる人の交流がもっと活発になると、福祉村はより「みんなの力でみんなの幸せを」という理念に近づけるのではないか、と思っています。
山本理事長の言動で印象に残っていることはありますか?
山本先生はいつも「社会が何を求めているのか。それに対して私たちは何ができるのか。常に考えなさい」と言っていました。そして、自らそれを実践されていました。
私が勤めていた頃は人手が十分でなく、先生は病院の近くにある職員寮に住んで入院患者さんの急変に対応していたんです。入院患者さんが急変したら夜中でも飛び起きてきて診療して、朝は9時から普通に診察を行う。「先生は一体いつ寝ているんだろう」と不思議になるほどの働きぶりでした。そのうえ、本をたくさん読まれるんです。地元の書店が毎日10冊ぐらい本を届けに来ていたのを覚えています。今思えば、先生はそうやって、社会が何を求めているのかを日々勉強されていたのでしょう。
私たちスタッフはそんな先生の姿を見ていますから、先生が社会福祉法人を設立すると言ったときも、「なんで?」と戸惑いはしても、反対はありませんでした。1980年に、認知症に関する相談を24時間電話で受け付ける「ボケ110番」を開設することになったときも、現場の仕事が増えるにもかかわらず、反対はなかったと記憶しています。医師会や世間からは「スタンドプレーをするな」と相当非難されましたが、先生の先見の明をよく知っていた私たちは、「先生が必要だと言うのなら、きっとそうなんだろう」と思ってついていっていました。