平田幸代

平田幸代
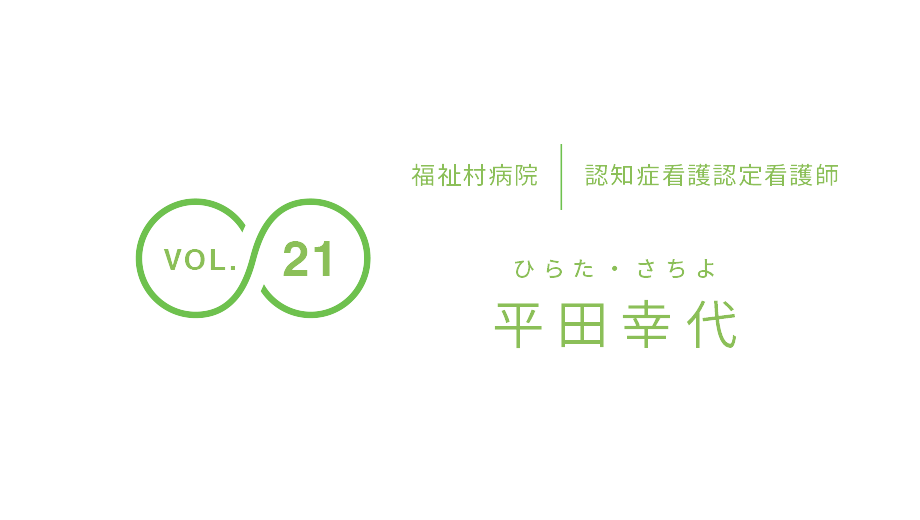
認知症看護認定看護師の資格を取得されるまでの経緯を教えてください。
中学時代、インテリアプランナーになりたいと考えていました。ただ、資格を取得できるのは20歳以上と年齢制限があって。じゃあ、20歳になるまでの5年間、何をしよう?と考えた結果選んだのが、5年制の看護師学校に通うことでした。20歳になるときには看護師の資格も取れるし、それからインテリアプランナーを目指したらいいと思ったわけです。今思えばとても気軽な選択でしたが(笑)、実習を始めてみると患者さんとのかかわりが楽しい。まわりからおだてられたのもあり、「自分は看護師に向いている」と思い始めました。結局そのまま看護師になり、福祉村病院に入職しました。
認知症看護認定看護師になったのは2015年です。山本看護総師長の勧めで半年間、東京の日本看護協会看護研修学校で学ばせていただき、資格を取得しました。

看護師として印象的な体験はありますか?
認知症看護認定看護師の資格を取る前のことです。担当している患者さんの中に、中心静脈カテーテル(以下、CV)で高カロリー栄養を注入されている患者さんがいらっしゃいました。その患者さんは寝たきりで、意思表示もほとんどできません。患者さんは今、何を感じているのだろう? 治療を続けたいと思っているのだろうか? そんな葛藤が常にありました。ところがある日、お風呂介助を終えてCVをつなごうとしたときに、その患者さんが私を見て声を出したのです。
「もう、いいよ」
大変な言葉を聞いてしまったと感じました。驚きのあまり、軽いパニックになりました。何が「もう、いい」のだろう? もう、お風呂は要らないという意味なのか、CVはつなげないでほしいという意味なのか、あるいは、もう生かさないでほしいという意味なのか。
その患者さんはそれきり話すことはなく、結局、答えは得られませんでした。どんな思いであのセリフを言ったのだろう。答えは得られないとわかっていても、今も時折、考えてしまうんです。
「常に笑顔を絶やさない」がモットーだと伺いましたが。
ご高齢者や認知症患者さんにとってつらいことのひとつに、「自分の居場所がないと感じる」ということがあると思います。ですから、私が笑顔で接することで、「ここにいてもいいんだ」と安心してほしいんです。疲れているときや、私生活で嫌なことがあっていら立っているときでも、患者さんに接するときは「笑顔」。安心できる居場所の提案のひとつと考え、そう決めています。
もうひとつ、何かあったら、自分一人で抱え込まないよう心がけています。一般的な病院では、特に看護総師長や部長など役職が上の人には、気軽に相談できない雰囲気があるようです。でも、福祉村病院は違います。
認知症看護認定看護師になったきっかけは、私が山本看護総師長に「福祉村病院にも認知症ケアのプロがいたらいいですね」と言ったことでした。私の発言を覚えていてくれた看護総師長が、5年ほど経ってから「認知症看護認定看護師の勉強をしてきて」とおっしゃって。当時は、「え? 私が!?」と驚きましたが(笑)。忙しくても悩みや意見に耳を傾けてくれる仲間と上司の存在に、いつも助けられています。
日頃のお仕事内容について教えてください。
認知症看護認定看護師の役割として、実践・指導・相談という3つの柱がありますので、この3つの柱に沿って仕事をします。実践というのは、自らが質の高いケアを提供すること。指導、助言というのは、簡単に言うと、認知症患者さんとそのご家族、また、認知症ケアの現場で働くスタッフに向けたコンサルティングですね。ご家族に退院後の生活についてアドバイスさせていただいたり、看護師や介護士さんに「患者さん視点のケアをしましょう」と伝えたり。認知症に限りませんが、看護の理想は、患者さん視点のケアを提供することです。でも、実際には、日々の業務を遂行するのに精一杯で、つい看護師視点のケアになってしまう。理想と現実との折り合いを一緒に考えて、実践していく。それが私の役目なんです。
ほかに、「認知症初期集中支援チーム」の仕事もあります。市の職員の方々と協力しながら、認知症の方、あるいはその疑いがあって、何かお困りごとのあるご本人とご家族のサポートを行っています。

